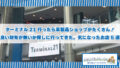「出かけようと思ったのに鍵が見つからない…」
「リモコンがいつもどこかにいってしまう…」
そんな経験、誰でも一度はありますよね。
日常生活の中で「探し物」に費やしている時間は、年間150時間以上とも言われています。つまり、1日あたり約25分も探し物をしている計算になります。
この「探すムダ時間」をなくすための効果的な方法が、「定位置管理」です。
この記事では、初心者でもすぐに実践できる定位置管理の基本ステップと、家族全員が使いやすい収納のコツをご紹介します!
「定位置管理」とは?

定位置管理とは、すべてのモノに「しまう場所=住所」を決めて管理する方法です。
この考え方を日常に取り入れることで、モノが迷子になることがなくなり、探し物のストレスも激減します。
【手順①】モノの「正しい定位置」を決めよう
まずは、身の回りのモノを見直し、それぞれに適切な“居場所”をつくってあげることから始めましょう。
定位置決めのポイント
・生活動線を意識する
例:「鍵」は玄関、「リモコン」はソファのそばなど
→ よく使う場所・タイミングに合わせることで出し入れがスムーズに!
・使用シーン別にまとめて管理する
例:外出用品(鍵・マスク・エコバッグ)を一緒に
→ シーンごとにモノをまとめると、効率もアップ!
・使用頻度によって収納場所を変える
→ 毎日使うモノは手が届く位置に、季節モノは上段や奥へ
よくある定位置アイデア
| アイテム | 定位置のおすすめ |
|---|---|
| 鍵 | 玄関の壁掛けフック、小物トレイ |
| リモコン | ソファ近くのボックス |
| メガネ | ベッドサイドやデスク上 |
| 書類 | ラベル付きファイルボックス |
| 文房具 | 引き出しに仕切りを使って |
【手順②】ラベルや視覚化で「誰でもわかる収納」に
定位置を決めたら、それを視覚的に明確にする工夫が大切です。特に家族がいる場合は、「誰が見てもわかる収納」になるよう工夫しましょう。
ラベルの活用方法
・文字ラベル
→ シンプルに「薬」「工具」「文具」などと表示
・写真ラベル
→ 子どもや高齢者でもわかるよう、実物の写真を貼る
・色分けラベル
→ 家族別、カテゴリ別に色を変えることで視認性UP!
特に中身が見えないボックスや引き出しには、写真やイラスト付きラベルを貼ると一目で内容が分かり、元に戻す意識も高まります。
生活動線に合わせた“自然収納”を目指そう

子どもやパートナーが「片づけない」のではなく、「どこに戻せばいいか分からない」ケースがほとんどです。
定位置管理は、誰でも迷わず片づけられる仕組み作りが重要です。
子ども向けの収納ポイント
・子どもの目線・手の届く場所に収納する
・カラフルなラベルやアイコンを活用する
・学用品・おもちゃを使用場所の近くに置く
こうすることで、片づけが習慣化し、「ママどこ?」と聞かれることも減っていきます。
定期的な見直しと改善も忘れずに!
一度定位置を決めたら終わりではありません。生活の変化や季節の移り変わりに応じて、定位置を見直すことも大切です。
見直しのタイミング例
・新学期・引っ越しなど生活環境の変化
・使っていないモノが増えた時
・収納場所にモノが戻らなくなってきた時
定位置管理を習慣化することで、モノの量も自然と見直すことができ、スッキリした暮らしが手に入ります。
探し物ゼロ生活は「定位置管理」から!

定位置管理を取り入れることで、日常の探し物がぐんと減り、ストレスフリーな毎日が実現できます。
✅ モノの住所を決める
✅ ラベルで視覚的にわかりやすく
✅ 生活動線を意識した配置
✅ 家族全員が「戻せる」収納を目指す
時間も心も余裕のある暮らしの第一歩として、ぜひ今日から「定位置管理」を始めてみませんか?